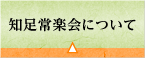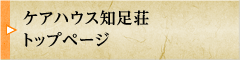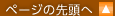果たせなかったスコッチでの決闘

第1回哈爾濱冰雪節開幕式(通算第8回)
平成4年1月
今では、世界的な冬の祭りとして知られるようになりました中国・哈爾濱市で開催されます「氷雪節」、その第1回が平成4年1月5日に全人代常務委員長 万里さんが開会を宣言して開幕しました。これに併せて新潟市代表団が招待され、4人の団員のひとりとして参加しました。たしか、北京の17~18カ国の大使館からも出席していたようですが、その他に新潟市とリバプール市が加わり、この2つのグループを一括りして行動しました。
そんな中で、「貴方の英語で十分通じる」と言って、プレスひとりを伴ったリバプール市長と意気投合して、哈爾濱から北京、そして帰国までの約1週間、私のブロークンな英語を我慢してもらって、通訳抜きでお付き合いしてくださいました。別れ際、私が着ていた英国ブランドのジャケットを見て喜び、何回も何回も、必ずリバプールを訪ねるよう念を押されました。
まもなく、リバプール市長 トレバー・スミスさんから手紙が届きました。そこには「中国での白酒が懐かしい。次は我が国のスコッチで」と書いてありました。
そんなことがあって、6年が過ぎた平成12年頃だと思いますが、たまたま、会社への投資先である東京中小企業投資育成会社の社長会の海外視察で、英仏独アイルランドの4カ国を訪れる機会がありました。ちょうど良い機会であり、イギリスで時間があれば、スミスさんにお会いしようと考えて、お土産を準備して出発したのですが、残念ながら予定が変更となり、リバプール市まで行くだけの時間的余裕がなくなりました。

トレーバ・スミス市長とハグの後 平成4年1月
持参したお土産をロンドンから送ろうとしましたが、それも果たせず帰国しました。後でお詫びの手紙を送りましたら、早速手紙が届きました。「我が英国最大の港湾都市の頭上を2回も通過し、他国へ行き、リバプールに降りないとは何事か。リバプールを抜きに英国を語ることなかれ。次は必ず立ち寄れ。そして1勝リードしている1対0の決着を着けよう」と恐れ入った挑戦状を頂きました。スミスさんは、中国の宴席で強い茅台酒での乾杯で、1勝したと確信しているようでした。

リバプール市長 トレーバ・スミスさん(中央)とプレス(右)、中山(左) 平成4年1月
それにしても、楽しい人です。こんな人達とだけなら、国際間の摩擦などは絶対に起きない。いずれ英国行きの機会を見つけ、スミスさんと「スコッチ」を武器に決闘せねばならないと考えて、30年ほど経過しました。
その目的のため、健康なうちにリバプールまで足を延ばす必要があるのですが、世の移り変わりの中で、時間が経ち過ぎ、イギリスを訪れる機会がありませんでした。スミスさんも高齢となり、市長職を引退し、悠々自適な余生を送っていることでしょう。
北京での別れ際、濃紺に赤の細いストライプの生地に「Liverpool」と印字された素敵なネクタイを、スミスさん自ら私の胸元に当て、「ぴったり合う」と言って下さったことが忘れられません。今も手元に残してあります。
旧ソ連時代のロシア極東ハバロフスクのホテルで

旧ソ連時代寒々としたホテルエントランス
昭和56年3月
未だ、旧ソ連もほとんど開放されていない昭和55年3月、ハバロフスク市のかつての国営ホテル「インツーリスト」の混み合ったロビーで、酒臭いロシア人が英語で話しかけてきました。「君は日本人か?」と訊く。日本人だと答えたら、「よくこんな国に来たな!何しに来た?」と言いました。
「初めての旧ソ連の旅で、ウズベク・タジク旅行の帰りだ」と答えますと、「あの地域はロシアではない」と言います。
「どうして?」「共産党が勝手に支配していたのだ」「ロシアは違う」「第二次大戦後の戦後処理がおかしい」「私の親父は第二次大戦が終わるそれまで、中国の青島でレストランをやっていた。その時は日本の支配だったが、秩序が保たれ、商売もものすごく繁盛していた」「それがだ! 強制的にロシア極東へ移住させられ、今の有様だ」「オレは一応、この国では仕事に就いているが、コミュニストは大嫌いだ」と耳打ちしました。
旧ソ連のことです。こんな状態の中で、どう答えてよいか分からなかったので、黙って聞くしかありませんでした。その頃は、れっきとした旧ソ連の時代。まさか、秘密警察にスパイか何かと間違われたら困ったものだと思いましたが、お咎めはなしでした。
ホテル周辺も含め、初めてのロシア極東の都 ハバロフスクはそれなりに美しいところです。ここは本当に日本に最も近いヨーロッパです。ハバロフスクは極東の中心であり、軍港で未解放だったウラジオストクと異なり、雰囲気も良く、旧ソ連の支配階級である上流階級はそれなりのプライドもあったようです。
この頃は統制経済の時代で物資も乏しく、日用品にも事欠くことが多かったと思います。
インツーリストホテルの周辺では外国人、とくに日本人にボールペンなどをせびる子供達が多くおりました。子供には必要ないはずですが、100円ライターを欲しがる子供達も。おそらく転売するのでしょうが、こんなものが大変な貴重品でした。

10年後の旧ソ連崩壊が想像できなかったが、その当時のロシア極東ハバロフスクの陽気な子供たち
昭和55年3月
外出すると男の子が4~5人一緒になって、しつこくつきまとい、ボールペンを要求しました。前方から来た3人程の共産党の幹部と見られる中年女性達が、何やらその子供達に厳しく注意して退散させていました。その意味は「ソ連の子供達は恥ずかしいことをしてはいけない」と、きつく叱っていたのでしょう。
旧ソ連のホテルは宿泊客にとって退屈な場所です。夕食後、部屋にいるだけでは物足りません。といってもホテル周辺には何もありません。できるのはホテルの地下にあるバーで一杯飲むことくらいです。
旧ソ連時代でしたが、地下の大広間は西欧のクラブのようになっており、片側に長いカウンターがあり、数十人は一度に腰掛けることができます。フロアには丸テーブルと椅子を組み合わせたものが多数あり、今なら中国人でしょうが、当時はヨーロッパ系の客が多く、そこへ数人の若い女性達のグループがたむろしていました。シャンペンやカクテル、ビールを欲しがるので適当にご馳走し、彼女らとの会話を楽しんでいたようです。こうしないと店が成り立たないのでしょう。
旧ソ連崩壊までは、その女性達をホテルの外へ連れ出すことはなかったようですが、旧ソ連の崩壊とともに乱れてゆきました。
組織的になり、一時はロビーの中までが斡旋所のようになっていて、ロビーを横切るのが大変だったこともあります。

且つて偉容を誇ったハバロフスクインツーリストホテル全景
昭和56年3月
ここ以外に外国人用ホテルがなかったので、それから20年間に5~6回このホテルのお世話になりましたが、忙しさにかまけて、その後を詮索する余裕はありませんでしたが、数年前も経済ミッションで訪れ、このホテルに泊まったが、表向きは平穏であったが、おそらく本当の地下に潜ってしまったのでしょう。
旧ソ連時代に地位のあった人でも、政治に口を挟まねば高齢でも身分が保証されるようです。

元ロシア極東原材料研究所長 バクーリンさんと.政治に口出ししなければ高齢でも地位が保障される.現在はロシア
太平洋大学教授.ロシア極東経済ミッション、ハバロフスク・インツーリストホテルで 平成24年11月
30年来の友人 バクーリン博士もそんな立場にいて、80歳を過ぎても、れっきとした大学教授です。彼に以前の地下バーのことを尋ねましたが、全く分からないとのことです。しかし、すでにロシア極東でも黒社会化は進んでいたのが、何となく雰囲気が分かりました。